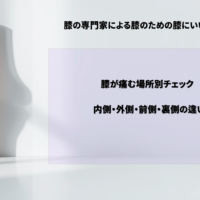膝の裏が痛い原因と日常生活でできる対策
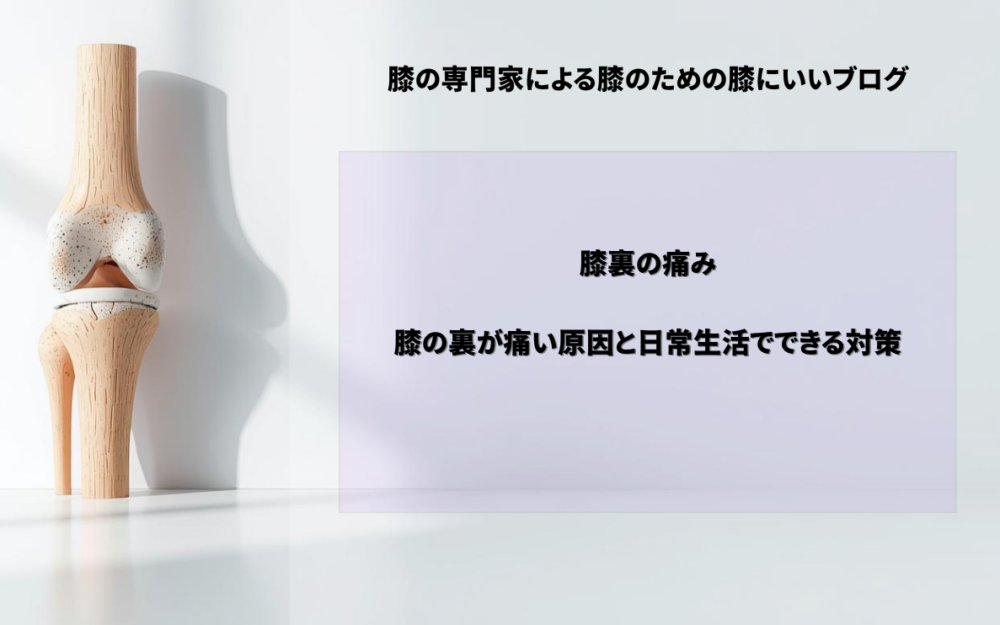
みなさまこんにちは!中央区八丁堀で膝の痛みに特化した治療院「脚の専門院リネアル」の見澤です!
膝の専門治療を行っている当院にはたくさんの膝の痛みでお悩みの方が来院されます。
いわゆる変形性膝関節症では、膝の内側が痛い、中の方が痛いという方が最もおいのですが、その中で膝の裏側が痛いという方も少なくありません。
膝の裏の痛みは、日常生活の中で意外と多くの方が経験する症状です。立ち仕事や長時間のデスクワーク、スポーツ活動など、さまざまな場面で膝裏に負担がかかることがあります。
そこで今回の記事では、膝の裏が痛む原因と、自宅でできる対策について専門的な視点から解説します。
目次
ベーカー嚢腫
半月板損傷
筋肉のこわばり(ハムストリングスなど)
その他の原因
ハムストリングスのストレッチ
ふくらはぎのストレッチ
膝裏のセルフマッサージ
アイシングと温熱療法
テーピングとサポーター
正しい座り方
歩き方のポイント
立ち姿勢の改善
寝る時の姿勢
運動習慣の工夫
体重管理
こんな症状があれば早めに受診
受診する診療科
病院で行われる主な検査
病院での治療法
治療後のリハビリテーション
1.膝の裏が痛むときに考えられる主な原因
膝の裏の痛みには、いくつかの代表的な原因があります。痛みの性質や発症のタイミングによって原因が異なるため、まずは自分の症状を理解することが大切です。
ベーカー嚢腫
ベーカー嚢腫(のうしゅ)は、膝の裏に液体が溜まって腫れる状態です。正式には「膝窩嚢腫(しっかのうしゅ)」と呼ばれ、膝関節内の滑液が後方に漏れ出て袋状に溜まることで発症します。
主な症状
・膝の裏に柔らかい膨らみを感じる
・膝を曲げると圧迫感や痛みがある
・長時間立っていると症状が悪化する
・ふくらはぎまで痛みが広がることもある
変形性膝関節症や関節リウマチ、半月板損傷などの膝の疾患がある場合に併発しやすく、40代以降の方に多く見られます。小さなベーカー嚢腫であれば自然に消失することもありますが、大きくなると日常生活に支障をきたすこともあります。
半月板損傷
半月板は膝関節の内側と外側にあるC字型の軟骨組織で、クッションの役割を果たしています。この半月板が損傷すると、膝の裏側に痛みが生じることがあります。
主な症状
・膝の曲げ伸ばし時に引っかかる感じがある
・膝の裏から内側にかけて鋭い痛みがある
・膝に水が溜まることがある
・「カクン」という音やクリック音がする
スポーツ中の急な方向転換やジャンプ着地、しゃがみ込む動作で損傷することが多く、若年層から中高年まで幅広い年齢層で発症します。加齢による変性でも起こりやすく、特に40代以降は日常的な動作でも損傷のリスクが高まります。
筋肉のこわばり(ハムストリングスなど)
膝の裏の痛みで最も多い原因の一つが、ハムストリングス(太もも裏の筋肉群)のこわばりや緊張です。デスクワークや長時間の運転など、同じ姿勢を続けることで筋肉が硬くなり、膝裏に痛みを感じます。
主な症状
・膝の裏が張ったような感覚がある
・朝起きた時や長時間座った後に痛みが強い
・前屈すると太もも裏から膝裏にかけて突っ張る
・運動不足や冷えで症状が悪化する
ハムストリングスは膝裏を通過して下腿の骨に付着しているため、この筋肉が硬くなると膝裏に直接的な負担がかかります。特に運動不足の方や、柔軟性が低下している方に多く見られます。
その他の原因
・膝窩筋腱炎
膝の裏にある小さな筋肉(膝窩筋)の炎症で、下り坂を歩くときや階段を降りるときに痛みが強くなります。
・静脈血栓症
膝裏の静脈に血栓ができると、腫れと痛みが生じます。長時間の飛行機移動後などに注意が必要です。
・リンパ節の腫れ
足の感染症やケガにより、膝裏のリンパ節が腫れて痛むことがあります。
2.膝の裏の痛みを和らげるストレッチとケア
自宅で簡単にできるストレッチとセルフケアをご紹介します。痛みが強い場合は無理をせず、できる範囲で行ってください。
ハムストリングスのストレッチ
・座位でのストレッチ
ⅰ)床に座り、片足を伸ばしてもう片方の足は曲げる
ⅱ)伸ばした足のつま先を天井に向ける
ⅲ)背筋を伸ばしたまま、ゆっくりと上体を前に倒す
ⅳ)太もも裏から膝裏に伸びを感じたら20〜30秒キープ
※反対側も同様に行う

・立位でのストレッチ
ⅰ)椅子や台に片足のかかとを乗せる
ⅱ)膝を軽く曲げた状態から、ゆっくりと膝を伸ばす
ⅲ)膝裏に伸びを感じたら15〜20秒キープ
※1日3セット、両足で行う
ふくらはぎのストレッチ
ふくらはぎの筋肉も膝裏に影響を与えるため、併せてケアすることが重要です。
ⅰ)壁に手をつき、片足を後ろに引く
ⅱ)後ろ足のかかとを床につけたまま、前足に体重をかける
ⅲ)ふくらはぎから膝裏にかけて伸びを感じたら20〜30秒キープ
※反対側も同様に行う
膝裏のセルフマッサージ
ⅰ)椅子に座り、膝を軽く曲げる
ⅱ)両手の親指以外の4本の指で膝裏を優しく押す
ⅲ)膝裏の中央から外側に向かって、円を描くようにマッサージ
※1回5分程度、痛みのない範囲で行う
アイシングと温熱療法
急性期(痛みが出て2〜3日)
腫れや熱感がある場合は、氷のうや冷却パッドで15〜20分冷やします。1日3〜4回行うと炎症を抑える効果があります。
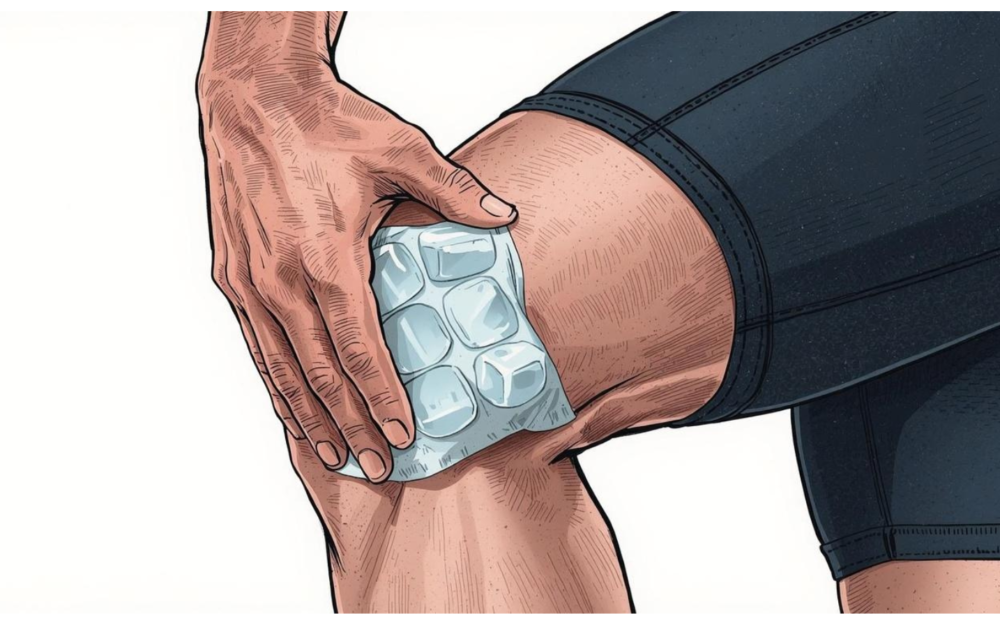
慢性期(痛みが1週間以上続く場合)
温タオルや温熱パッドで膝裏を温めることで、血行が促進され筋肉の緊張が和らぎます。入浴時にゆっくり湯船に浸かることも効果的です。
テーピングとサポーター
膝裏の負担を軽減するために、キネシオテープや膝サポーターを活用することも有効です。特にスポーツや長時間の立ち仕事をする際には、予防的に使用すると良いでしょう。
3.日常生活での工夫(座り方・歩き方・姿勢)
日常の何気ない動作を見直すことで、膝裏への負担を大幅に減らすことができます。
正しい座り方
デスクワーク時
椅子に深く腰掛け、背もたれに背中をつける
膝の角度は90度を保ち、足裏全体を床につける
長時間同じ姿勢を避け、1時間に1回は立ち上がって歩く
足を組む習慣は膝裏の血流を妨げるため控える
床に座る時
正座やあぐらを長時間続けない
座椅子を使用する場合は、膝を伸ばせる姿勢を取り入れる
横座りは膝に負担がかかるため避ける
歩き方のポイント
目線は前方に向け、背筋を伸ばす
かかとから着地し、つま先で蹴り出す
歩幅は無理に広げず、自然なリズムで歩く
膝を過度に伸ばしきらず、軽く余裕を持たせる
階段の上り下り
手すりを使って膝への負担を分散させる
下りる際は特にゆっくりと、膝をコントロールしながら降りる
痛みがある時は一段ずつ両足を揃えて降りる
立ち姿勢の改善
長時間立つ場合
両足に均等に体重をかける
片足重心を避け、こまめに体重を移動させる
クッション性の良い靴を選ぶ
可能であれば足元に低い台を置き、交互に足を乗せる
寝る時の姿勢
・仰向け
膝の下に小さめのクッションを入れると、膝裏の緊張が和らぎます。
・横向き
両膝の間にクッションを挟むと、膝への負担が軽減されます。
運動習慣の工夫
適度な運動
・ウォーキングは1日20〜30分を目安に
・水中ウォーキングは膝への負担が少なくおすすめ
・ストレッチは毎日続けることが重要
避けるべき動作
・急な方向転換やジャンプ
・重い荷物を持っての階段昇降
・深いスクワットや膝を深く曲げる動作の繰り返し
体重管理
体重が1kg増えると、歩行時には膝に約3kgの負担がかかると言われています。適正体重を維持することは、膝裏への負担軽減に直結します。

4.病院での治療と受診の目安
自宅でのケアで改善しない場合や、特定の症状がある場合は、専門医の診察を受けることをお勧めします。
こんな症状があれば早めに受診
すぐに受診が必要な症状
・膝裏に明らかな腫れがあり、日に日に大きくなる
・激しい痛みで歩けない、体重をかけられない
・膝が動かなくなる、曲げ伸ばしができない
・発熱を伴う痛みや腫れ
・ふくらはぎの痛みと腫れ(血栓症の可能性)
1〜2週間様子を見ても改善しない場合
・セルフケアを続けても痛みが変わらない
・日常生活に支障が出ている
・夜間痛で眠れない
・しびれや感覚の異常を伴う
受診する診療科
整形外科
骨や関節、筋肉の問題を専門とし、膝の痛みの大部分はここで診療します。レントゲンやMRI検査が可能です。
病院で行われる主な検査
・問診と触診
痛みの部位、発症時期、きっかけなどを詳しく聞き、実際に膝を触って腫れや圧痛を確認します。
・画像検査
レントゲン:骨の変形や関節の状態を確認
MRI:半月板や靭帯、嚢腫などの軟部組織を詳しく観察
超音波検査:ベーカー嚢腫や腱の炎症を確認
・血液検査
関節リウマチなどの炎症性疾患が疑われる場合に実施します。
病院での治療法
保存療法
・消炎鎮痛剤の内服や湿布
・ヒアルロン酸やステロイドの関節内注射
・理学療法(リハビリテーション)
・装具療法(サポーターや足底板)
ベーカー嚢腫の治療
小さいものは経過観察
大きく症状が強い場合は穿刺(針で液体を抜く)
原因となる膝関節疾患の治療が重要
半月板損傷の治療
軽度:保存療法とリハビリ
重度:関節鏡手術(小さな傷で行う内視鏡手術)
・手術療法
保存療法で改善しない重度の半月板損傷や、変形性膝関節症が進行している場合は手術を検討します。現在は関節鏡を使った低侵襲な手術が主流で、入院期間も短縮されています。
・治療後のリハビリテーション
病院での治療後は、理学療法士による専門的なリハビリテーションが重要です。筋力トレーニング、可動域訓練、歩行訓練などを通じて、膝の機能回復と再発予防を目指します。
5.まとめ
膝の裏の痛みは、ベーカー嚢腫や半月板損傷、筋肉のこわばりなど、さまざまな原因で起こります。多くの場合、適切なストレッチやセルフケア、日常生活の工夫で改善が期待できます。
特に重要なのは、早期の対処と継続的なケアです。痛みを我慢して放置すると症状が悪化し、治療期間も長くなってしまいます。自宅でのケアで改善しない場合や、腫れや激しい痛みがある場合は、早めに整形外科を受診しましょう。
膝は日常生活で常に負担がかかる関節です。今日からできる小さな工夫を積み重ねることで、健康な膝を保ち、快適な生活を送ることができます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最後までお読みいただきありがとうございました。
皆様により詳しく脚の健康のことやRinealのことを知っていただくために、LINE公式アカウント、Instagramで情報発信を行っております。ご興味を持っていただけた方はぜひお友達登録、フォローよろしくお願いします!
また、ご予約をご希望される方はこちら(予約ページはこちら)からご予約いただけます。
ご質問やお問い合わせお待ちしております!
次回の記事もぜひご覧ください!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~